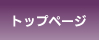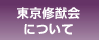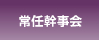第698回 二木会のご案内
『教え方大全 ~子供、孫、部下、後輩へ、あなたの考えを伝えるために~』
(講師:「小論ラボ」主宰/大学受験小論文講師 平成19年卒 菊池秀策さん)
初春の候、館友の皆さまにおかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、令和8年2月の二木会は、平成19年ご卒業の菊池秀策(きくち しゅうさく)さんに、『教え方大全~子供、孫、部下、後輩へ、あなたの考えを伝えるために~』と題してご講演をいただきます。
菊池さんは、早稲田大学法学部をご卒業後、大手電機メーカー関連企業で製品規格立案業務に従事する傍ら、経済的な理由で予備校などに通うことが困難な高校生達の学習をボランティアとして支援し志望校への合格を実現されたご経験を機に、教育を通した社会への貢献を決意して予備校講師へと転身されました。東京都内の大手予備校や福岡での複数の予備校での勤務を経て、平成25年には小論文専門予備校「小論ラボ」を自ら創設され、初年度から国立大学医学部合格者を輩出します。それ以降、受験生の様々な能力と人物像を測る総合型選抜(いわゆるAO入試)が大きな比重を占める現代において、小論文対策はもちろんのこと、面接対策を含めた総合的な入試対策により、受講生の皆さんの難関大学への合格を毎年実現され、医学部専門予備校などにも出講されています。また、学習参考書の執筆にも取り組まれ、KADOKAWAやGakkenから7冊の書籍が刊行されています。
「小論ラボ」では、従来の一斉指導とは一線を画した完全個別での生徒とのディスカッションを中心に、幅広い受験生のそれぞれの個性に対応した、思考力、判断力、表現力を養成する指導を日々実践されているとのことです。今回のご講演では、大学入試指導のプロとして若い世代と常に接しておられる菊池さんに、「何度も言ったのに伝わらない」「若者の感覚がわからない」といった、家庭や職場で誰もが直面する悩みの解決方法として、「デジタルネイティブ世代にも響く『教え方』の極意」についてお話しをいただきます。信頼関係の築き方から、曖昧さをなくす「言語化」、確実に定着させる「再現」の技術まで、誰でも使うことができる12のメソッドを公開いただく予定です。また、以前とは大きく異なり、受験生たちの個性を活かした指導が必要となる「大学受験のいま」についても、お時間が許せばお話をいただきたいと考えております。館友の皆さまとともに、皆さまの知識と経験を次世代へ正しく伝え、その成長を引き出すための「教え方」を考える機会となれば幸いです。
なお、学士会館の休館により、令和7年1月より「ホテルグランドヒル市ヶ谷」(市ヶ谷駅から徒歩3分)に会場が変更となっております。これまでと同様に、会場参加とオンライン参加を選択可能なハイブリッド方式により開催し、講演会終了後には、同一建物内の会場にて有志による懇親会を開催することを予定しております。
多数の館友の皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
準備の都合上、お申し込みは令和8年2月10日(火)正午迄にお願いいたします。
東京修猷会 会 長 等 健次(昭和45年卒)
幹事長 原沢 由美(昭和58年卒)
第698回二木会講演会
テーマ:『教え方大全 ~子供、孫、部下、後輩へ、あなたの考えを伝えるために~』
講 師:菊池秀策(きくち しゅうさく)さん(平成19年卒)
日 時:令和8年2月12日(木)(受付18:30~ 講演19:00~)
場 所:ホテルグランドヒル市ヶ谷 西館3階 オリオンの間
東京都新宿区市谷本村町4-1 電話03-3268-0111
JR・有楽町線・南北線・都営新宿線 市ヶ谷駅 徒歩3分
(有楽町線・南北線は7番出口を、都営新宿線は4番出口をご利用ください)
※ホテル本体東館の左隣の西館3階での開催です。地上レベルが地下1階扱いのため、左側の階段を上がった1階からのご入場をお勧めします(地上レベルからご入場の場合、飲食店街を奥に抜けるとエレベーターがあります)。
※詳細はこちらをご覧ください。
会 費: (会場参加)1,500円 (オンライン参加)1,000円
*70歳以上および学生の方は、会場参加/オンライン参加のいずれも無料
以下の留意事項を十分ご確認の上、それぞれのご参加方法等に応じたチケットによりお申込みください。
参加申し込みはこちらからお願いします
※パスワードはご案内メールに記載されております。
(申込期限:令和8年2月10日(火)正午まで)
<留意事項>
1.お申込み方法について
• お申込みのシステムとして、お支払を伴わない場合を含め、以下のteketの仕組みを採用しています(以前採用していたPass Marketによるお申込みについては、仕様変更によりYahoo! JAPAN IDの登録とクレジットカードの登録が必須となったため廃止し、teketにお申込み方法を統一させていただきました。何卒ご了承ください)。
• 会員登録を行った上でのお申込みと、会員登録をされないままでのお申込みが可能です。詳細はこちらをご参照ください。
なお、上記のご案内にはチケットの提示について記載がありますが、当日のご参加にチケットの提示は不要ですので、会場でのご参加の場合、受付でお名前と卒業年度をお知らせください。また、チケットの譲渡はできません。
• ご案内メール記載のパスワードによるエントリー後、画面右側(PCの場合)または下側(スマートフォンの場合)に表示される「自由席チケットを選択」をクリックしてください。以下2.の区分によるチケットが表示されますので、このうち、それぞれのご参加方法、お支払の有無・方法に応じたチケット1枚のみをご選択いただき、手順に従いお申込みの手続きを行ってください。
お申込みに際して必要となるメールアドレスの認証手続について、こちらをご参照ください。
なお、スマートフォンでのお申込みの場合、認証コードが記載されたメールを開くためにメールアプリ内で開いているteketのページを閉じなければならなくなってしまうことがあるため、teketのページを、メールのリンクからではなく東京修猷会のページのリンク等からブラウザアプリで開いていただいた上で、お申込みを進めていただくことをお勧めします。
• 会員登録を行わない場合には、クレジットカード決済(VISA,Master,JCB,Amex, Diners)のみご利用いただけます。
• 会員登録を行われた場合には、上記のクレジットカード決済のほか、コンビニ決済が可能です。コンビニ決済は手数料(220円)が必要となります。
2.チケットの区分とオンライン視聴用のURLのお知らせについて
• チケットの区分は以下のとおりです。
①会場参加:70歳以上および学生の方(無料)
②会場参加:一般(会費1,500円を申込時にお支払いただく場合)
③会場参加:一般(会費1,500円を現地受付でお支払いただく場合)
④オンライン参加:70歳以上および学生の方(無料)
⑤オンライン参加:一般(会費1,000円を申込時にお支払いただきます)
オンライン参加 ④または⑤でお申込みいただいた方には、2月10日(火)を目途に、講演当日の視聴に必要なURLをご指定のメールアドレスに送付いたします。
なお、翌日2月11日(水)になってもメールが届いていない場合は、2月12日(木)12時までにこちらをクリックいただきお問い合わせください。
• 会場参加 ①または②でお申込みいただいた方にも、これとあわせ、オンライン視聴用のURLをお送りいたします。当日のご都合により会場への来場が難しくなった場合も、オンラインでご参加いただくことが可能です(この場合も差額のご返金は致しかねますので、何卒ご了承ください)。
• 会費お支払い手続き後は視聴の有無にかかわらずキャンセル/払い戻しはできないこと、また通信環境の状況等により画像・音声が安定しない場合があることにつき、あらかじめご了承ください。なお、運営側の責より視聴ができなかった場合は、誠意をもって対応させていただきます。
3.その他留意事項について
• お申込み方法についてご不明な点などございましたら、こちらをクリックいただきお問い合わせください。
- 第698回 二木会のご案...
(2026/02/01)
- 第697回 二木会のご案...
(2025/12/30)
- 令和7年度二木会忘年会開...
(2025/12/29)
- 令和7年度二木会忘年会の...
(2025/11/14)
- 第696回 二木会のご案...
(2025/10/10)
- 第695回 二木会のご案...
(2025/09/23)
- 第678回二木会講演記録
(2025/09/20)
- 第677回二木会講演会記...
(2025/09/07)
- 第675回二木会講演会記...
(2025/08/21)
- 第693回 二木会のご案...
(2025/06/12)
- 第692回 二木会のご案...
(2025/04/10)
- 第691回二木会・新入会...
(2025/03/13)
- 第690回 二木会のご案...
(2025/02/13)
- 第689回 二木会のご案...
(2025/01/09)
- 第688回 二木会のご案...
(2024/12/12)
- 令和6年 二木会忘年会の...
(2024/11/14)
- 第687回 二木会のご案...
(2024/10/10)
- 第686回 二木会のご案...
(2024/09/07)
- 令和5年度二木会忘年会開...
(2024/09/01)
- 第684回二木会のご案内
(2024/06/01)
- 第683回二木会のお知ら...
(2024/04/06)
- 第682回二木会・新入会...
(2024/03/03)
- 第673回二木会講演会・...
(2024/02/21)
- 第681回二木会のご案内
(2024/01/24)
- 第680回二木会のご案内
(2024/01/11)
- 第679回二木会のご案内
(2023/12/07)
- 令和5年 二木会忘年会の...
(2023/11/06)
- 第678回二木会のご案内
(2023/10/02)
- 第672回二木会講演会記...
(2023/09/18)
- 第677回二木会のご案内
(2023/08/26)
- 第671回二木会講演会記...
(2023/08/20)
- 第670回二木会講演会記...
(2023/06/22)
- 第675回二木会のご案内
(2023/06/09)
- 第669回二木会講演会記...
(2023/05/15)
- 第668回二木会講演会記...
(2023/05/08)
- 令和4年度二木会忘年会開...
(2023/04/23)
- 第674回二木会のご案内
(2023/04/14)
- 第673回二木会・新入会...
(2023/03/13)
- 第672回二木会のご案内
(2023/02/09)
- 第671回二木会のご案内
(2023/01/10)
- 第665回二木会講演会記...
(2022/12/13)
- 第670回二木会のご案内
(2022/12/04)
- 【再掲】令和4年 二木会...
(2022/12/02)
- 第666回二木会講演会記...
(2022/11/12)
- 第664回二木会講演会・...
(2022/11/08)
- 令和4年 二木会忘年会の...
(2022/11/06)
- 第663回二木会講演会記...
(2022/10/14)
- 第669回二木会のご案内
(2022/10/07)
- 第662回二木会講演会記...
(2022/10/07)
- 第661回二木会講演会記...
(2022/10/07)
- 第668回二木会のご案内
(2022/09/07)
- 第660回二木会講演会記...
(2022/09/01)
- 第657回二木会講演会記...
(2022/09/01)
- 第659回二木会講演会記...
(2022/08/29)
- 第666回二木会のご案内
(2022/06/10)
- 第665回二木会のご案内
(2022/04/14)
- 第664回二木会・新入会...
(2022/03/13)
- 第663回二木会のご案内
(2022/02/12)
- 第662回二木会のご案内
(2022/01/14)
- 第661回二木会のご案内
(2021/12/11)
- 第660回二木会のご案内
(2021/11/16)
- 第656回二木会講演会記...
(2021/11/13)
- 第659回 二木会のご案...
(2021/09/11)
- 第655回二木会講演会記...
(2021/09/08)
- 第657回 二木会のご案...
(2021/06/07)
- 第656回 二木会のご案...
(2021/04/17)
- 第655回 二木会のご案...
(2021/02/19)
- 第654回二木会講演会記...
(2021/02/10)
- 【重要:開催方式変更】2...
(2021/01/09)
- 第654回 二木会のご案...
(2020/12/06)
- 第653回二木会講演会記...
(2020/06/12)
- 5月14日(木)二木会の...
(2020/04/13)
- 4月9日(木)二木会・新...
(2020/03/27)
- 第654回 二木会・新入...
(2020/03/11)
- 3月12日(木)二木会の...
(2020/03/01)
- 第648回二木会講演会記...
(2020/02/15)
- 第647回二木会講演会記...
(2020/02/15)
- 第654回 二木会のご案...
(2020/02/06)
- 第651回二木会講演会記...
(2020/01/28)
- 第653回 二木会のご案...
(2020/01/10)
- 第603回二木会講演会記...
(2020/01/05)
- 第602回二木会講演会記...
(2020/01/05)
- 第601回二木会講演会記...
(2020/01/05)
- 第599回二木会講演会記...
(2020/01/05)
- 第598回二木会講演会記...
(2020/01/05)
- 第650回二木会講演会(...
(2019/12/06)
- 第652回 二木会のご案...
(2019/12/06)
- 令和元年二木会忘年会のご...
(2019/11/08)
- 第651回 二木会のご案...
(2019/10/11)
- 第650回 二木会のご案...
(2019/09/03)
- 第646回二木会講演会記...
(2019/07/01)
- 第648回 二木会のご案...
(2019/06/04)
- 第645回二木会講演会記...
(2019/05/16)
- 第644回二木会講演会記...
(2019/05/16)
- 第643回二木会講演会記...
(2019/05/16)
- 第642回二木会講演会記...
(2019/05/16)
- 第641回二木会講演会記...
(2019/05/16)
- 第647回 二木会のご案...
(2019/04/08)
- 第646回 二木会・新入...
(2019/03/05)
- 第645回 二木会のご案...
(2019/02/12)
- 第644回 二木会のご案...
(2019/01/07)
- 第643回 二木会のご案...
(2018/12/07)
- 第639回二木会講演会記...
(2018/11/14)
- 平成30年二木会忘年会の...
(2018/10/30)
- 第642回 二木会のご案...
(2018/10/14)
- 第638回二木会講演会記...
(2018/10/01)
- 第637回二木会講演会記...
(2018/09/25)
- 第636回二木会講演会記...
(2018/09/25)
- 第635回二木会講演会記...
(2018/09/25)
- 第634回二木会講演会記...
(2018/09/20)
- 2017年度二木会忘年会...
(2018/09/15)
- 第641回 二木会のご案...
(2018/08/21)
- 第633回二木会講演会記...
(2018/08/19)
- 第639回二木会のご案内
(2018/06/09)
- 第638回二木会のご案内
(2018/04/14)
- 第632回二木会講演会記...
(2018/03/26)
- 第637回二木会・新入会...
(2018/03/10)
- 第636回二木会のご案内
(2018/02/10)
- 第635回二木会のご案内
(2018/01/15)
- 第634回二木会のご案内
(2017/12/15)
- 平成29年二木会忘年会の...
(2017/11/14)
- 第633回二木会のご案内
(2017/10/16)
- 第632回二木会のご案内
(2017/08/30)
- 第630回二木会講演会記...
(2017/08/27)
- 第629回二木会講演会記...
(2017/08/27)
- 第628回 二木会・新入...
(2017/08/27)
- 第11回 「Salon ...
(2017/07/13)
- 第627回二木会講演会記...
(2017/06/08)
- 第630回二木会のご案内
(2017/06/08)
- 第629回二木会のご案内
(2017/04/09)
- 第626回二木会講演会記...
(2017/04/09)
- 第628回二木会・新入会...
(2017/03/04)
- 第625回二木会講演会記...
(2017/02/24)
- 2016年度二木会忘年会...
(2017/02/10)
- 第627回二木会のご案内
(2017/02/09)
- 第624回二木会講演会記...
(2017/01/30)
- 第623回二木会講演会記...
(2017/01/30)
- 第626回二木会のご案内
(2017/01/12)
- 第625回二木会のご案内
(2016/12/04)
- 平成28年二木会忘年会の...
(2016/11/13)
- 第624回二木会のご案内
(2016/10/14)
- 第623回二木会のご案内
(2016/09/09)
- 第621回二木会講演会記...
(2016/08/24)
- 第620回二木会講演会記...
(2016/08/05)
- 第619回二木会講演会記...
(2016/06/13)
- 第618回二木会講演会記...
(2016/06/13)
- 第621回二木会のご案内
(2016/06/11)
- 第620回二木会のご案内
(2016/04/14)
- 第617回二木会講演会記...
(2016/04/04)
- 第616回二木会講演会記...
(2016/03/29)
- 第619回二木会・新入会...
(2016/03/10)
- 2015年度二木会忘年会...
(2016/02/24)
- 第615回二木会講演会記...
(2016/02/24)
- 第618回二木会のご案内
(2016/02/14)
- 第617回二木会のご案内
(2016/01/15)
- 第614回二木会講演会記...
(2015/12/22)
- 第616回二木会のご案内
(2015/12/11)
- 平成27年二木会忘年会の...
(2015/11/13)
- 第612回二木会講演会記...
(2015/10/17)
- 第615回二木会のご案内
(2015/10/09)
- 第614回二木会のご案内
(2015/09/13)
- 第611回二木会講演会記...
(2015/07/23)
- 東京修猷会 特別上映会の...
(2015/07/10)
- 第610回二木会講演会記...
(2015/06/28)
- 第612回二木会のご案内
(2015/06/13)
- 第609回二木会講演会記...
(2015/06/11)
- 第608回二木会講演会記...
(2015/06/09)
- 第607回二木会講演会記...
(2015/04/27)
- 第611回二木会のご案内
(2015/04/10)
- 第610回二木会・新入会...
(2015/03/12)
- 第609回二木会のご案内
(2015/02/12)
- 2014年度二木会忘年会...
(2015/01/16)
- 第600回二木会記念大会...
(2015/01/14)
- 第608回二木会のご案内
(2015/01/08)
- 第606回二木会講演会記...
(2015/01/08)
- 第605回二木会講演会記...
(2015/01/07)
- 第607回二木会のご案内
(2014/12/11)
- 2014年二木会忘年会の...
(2014/11/13)
- 第606回二木会のご案内
(2014/10/09)
- 第605回二木会のご案内
(2014/09/10)
- 第8回 「Salon d...
(2014/07/16)
- 第603回二木会のご案内
(2014/06/14)
- 第602回二木会のご案内
(2014/04/12)
- 第601回二木会・新入会...
(2014/03/17)
- 東京修猷会二木会第600...
(2014/03/01)
- 第599回二木会のご案内
(2014/01/10)
- 2013年度二木会忘年会...
(2014/01/09)
- 第597回二木会講演会記...
(2013/12/26)
- 第598回二木会のご案内
(2013/12/12)
- 第596回二木会講演会記...
(2013/12/10)
- 2013年二木会忘年会の...
(2013/11/14)
- 第597回二木会のご案内
(2013/10/09)
- 第596回二木会のご案内
(2013/09/13)
- 第594回二木会講演会記...
(2013/09/05)
- 第594回二木会のご案内
(2013/06/16)
- 第593回二木会講演会記...
(2013/06/06)
- 第592回二木会講演会記...
(2013/05/25)
- 第591回二木会講演会記...
(2013/05/11)
- 第593回二木会のご案内
(2013/04/17)
- 第590回二木会講演会記...
(2013/03/24)
- 第592回二木会・新入会...
(2013/03/16)
- 第591回二木会のご案内
(2013/02/16)
- 第589回二木会講演会記...
(2013/02/13)
- 第590回二木会のご案内
(2013/01/16)
- 2012年度二木会忘年会...
(2013/01/04)
- 第589回二木会のご案内
(2012/12/13)
- 第588回二木会講演会記...
(2012/12/13)
- 2012年二木会忘年会の...
(2012/11/10)
- 第587回二木会講演会記...
(2012/11/09)
- 第588回二木会のご案内
(2012/10/13)
- 第587回二木会のご案内
(2012/09/13)
- 第585回二木会講演会記...
(2012/08/07)
- 第584回二木会講演会記...
(2012/06/13)
- 第585回二木会のご案内
(2012/06/07)
- 第582回二木会講演会記...
(2012/04/26)
- 第584回二木会のご案内
(2012/04/16)
- 第583回二木会のご案内
(2012/03/13)
- 第580回二木会講演会記...
(2012/03/07)
- 第582回二木会のご案内
(2012/02/13)
- 第581回二木会のご案内
(2012/01/15)
- 2011年度二木会忘年会...
(2012/01/09)
- 第579回二木会講演会記...
(2011/12/25)
- 第580回二木会のご案内
(2011/12/12)
- 第578回二木会講演会記...
(2011/11/27)
- 2011年二木会忘年会の...
(2011/11/14)
- 第577回二木会講演会記...
(2011/10/26)
- 第579回二木会のご案内
(2011/10/16)
- 第578回二木会のご案内
(2011/09/11)
- 第576回二木会講演会記...
(2011/09/01)
- 第577回二木会のご案内
(2011/08/08)
- 第575回二木会講演会記...
(2011/06/28)
- 第576回二木会のご案内
(2011/06/09)
- 第574回二木会講演会記...
(2011/06/01)
- 第573回二木会講演会記...
(2011/05/31)
- 第575回二木会のご案内
(2011/04/15)
- 第572回二木会講演会記...
(2011/04/11)
- 第571回二木会講演会記...
(2011/02/25)
- 平成22年度二木会忘年会...
(2011/01/15)
- 第570回二木会講演会記...
(2011/01/09)
- 第569回二木会講演会記...
(2010/11/13)
- 第568回二木会講演会記...
(2010/10/30)
- 第570回二木会のご案内
(2010/10/18)
- 第569回二木会のご案内
(2010/09/16)
- 第568回二木会のご案内
(2010/08/20)
- 第567回二木会講演会記...
(2010/07/20)
- 第566回二木会講演会記...
(2010/07/06)
- 第565回二木会講演会記...
(2010/07/05)
- 第564回二木会講演会記...
(2010/07/04)
- 第563回二木会講演会記...
(2010/07/03)
- 第562回二木会講演会記...
(2010/07/02)
- 第567回二木会のご案内
(2010/06/21)
- 第566回二木会のご案内
(2010/04/10)
- 第565回二木会のご案内
(2010/03/16)
- 第564回二木会のご案内
(2010/02/18)
- 第563回二木会のご案内
(2010/01/16)
- 平成21年度二木会忘年会...
(2009/12/25)
- 第561回二木会講演会記...
(2009/12/15)
- 第560回二木会講演会記...
(2009/12/13)
- 第562回二木会のご案内
(2009/12/11)
- 2009年二木会忘年会の...
(2009/11/13)
- 第559回二木会講演会記...
(2009/10/24)
- 第561回二木会のご案内
(2009/10/08)
- 第560回二木会のご案内
(2009/09/26)
- 第559回二木会のご案内
(2009/08/18)
- 第555回二木会講演会記...
(2009/07/27)
- 第558回二木会のご案内
(2009/06/26)
- 第557回二木会講演会(...
(2009/06/24)
- 第556回二木会講演会の...
(2009/06/11)
- 第556回二木会講演会兼...
(2009/03/18)
- 第553回二木会講演会記...
(2009/03/05)
- 第552回二木会講演会記...
(2009/03/04)
- 第555回二木会のお知ら...
(2009/02/26)
- 平成20年度東京修猷会二...
(2009/02/25)
- 2008年二木会忘年会の...
(2009/02/24)
- 第551回二木会講演会報...
(2009/02/23)
- 第550回 二木会(石橋...
(2009/02/22)
- 第549回二木会講演会記...
(2009/02/21)
- 第548回二木会講演会記...
(2009/02/20)
- 第547回二木会 開催報...
(2009/02/19)
- 第546回二木会 開催報...
(2009/02/18)
- 第545回二木会 開催報...
(2009/02/17)
- 第544回二木会 開催報...
(2009/02/16)