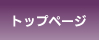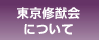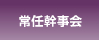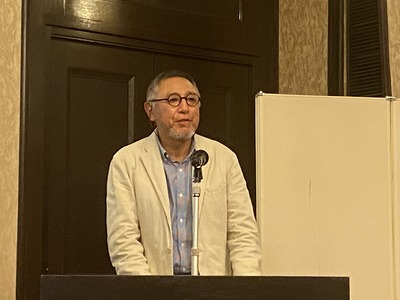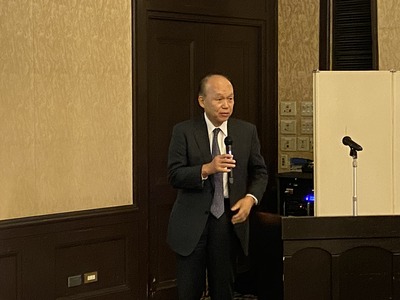第678回二木会講演記録
「指揮官の心得と責務~イラク復興支援、東日本大震災からの教訓」
講師:立花尊顕さん(昭和51年卒)
開催日時:令和5年年11月9日(木)19:00-20:00
〇古賀(司会) 本日の二木会は、昭和51年卒の立花尊顕(たちばなたかあき)さんに「指揮官の心得と責務~イラク復興支援、東日本大震災からの教訓」をテーマにご講演いただきます。
立花さんは昭和57年に防衛大学校をご卒業後、陸上自衛隊に入隊されました。東北方面総監部幕僚副長、自衛隊情報保全隊司令などの要職を歴任され、その間、イラク復興支援や東日本大震災などの大規模災害への派遣活動に従事されました。平成26年に退官後は、認定NPO法人「日本地雷処理を支援する会」のカンボジア現地事務所代表としてカンボジアでの地雷処理活動を支援され、現在も同会理事としてご活躍されています。
■講師紹介
〇養父 私と立花くんは、中学、修猷館、そしてラグビー部でも一緒でした。私たち昭和51年卒のラグビー部は、才能ある先輩と後輩に挟まれた年で、春の九州大会では中部地区予選で敗退し、全国大会の予選も、中部地区予選で福岡高校にも負けて県大会にも行けませんでした。同級生メンバーは、2年生の終わりには8人いましたが、3年生の九州大会が終わった後は4人に減ってしまいました。私もその時に辞めてしまったのですが、立花くんを含む4人は、その後も秋の全国大会まで続けて後輩たちを育てられました。そのおかげもあってちょうど2年後輩、つまり、われわれが3年生の時の1年生である昭和53年卒の皆さんが、県大会で優勝して花園に出ました。
立花くんは、当時の二丈町、福吉に生まれ育ち、ご実家はお米屋さんだったそうです。糸島は今では人気のある土地ですが、当時は室見川から向こうは、「ど田舎」でした。福岡寄りの今宿、周船寺でさえ田舎者扱いでしたが、さらにその向こうの福吉となると、福岡の最果て扱いで、そこから単線のディーゼルカーしかない筑肥線で1時間以上かけて通学されていました。
ラグビー部では立花くんはフォワードで、スクラムを組むときは、いつも率先して締まった甲高い声でみんなを引っ張っていました。でもそれ以外は寡黙で、人とあまりつるまないタイプでした。今思うと、ちょっと言い過ぎですが、高倉健のような感じで、「男は黙って」というタイプだったと思います。
立花くんとは、ずっと交流が途絶えていましたが、ラグビー部の縁で40年ぶりに再会しました。そして、今年の7月に、立花くんと同じく筑肥線の通学仲間だった白水朝日くんと3人で三軒茶屋で飲んだ時に、立花くんの経験話を聞いて、これはみんなに聞いてもらったほうがいいと、白水さんが東京修猷会の副会長の加藤さんにコンタクトしてくれて、今日の講演会が実現しました。今日はその白水さんが立花さんを紹介する予定だったのですが、出張になり、急きょ私が福岡から来た次第です。
■立花氏講演
〇立花 ど田舎出身の立花です。今日はこのような機会をいただき、また事務局のほうではいろいろ調整していただきありがとうございます。そして、福岡から出てきて紹介をしてくれた養父くんにも感謝申し上げます。今日は、諸先輩がおられる中ではありますが、「指揮官の心得と責務」ということで、イラク復興支援、それから東日本大震災の教訓について自分が経験したことや感じたことを率直にお話しさせていただきます。所々、自慢話と思われるようなところもあるかもしれませんが、そこはご容赦ください。
■はじめに
私は、1995年ぐらいから実際のオペレーションに参加する機会が多くなりました。その背景には自衛隊の役割の変化もあります。1989年の冷戦終結までは、「存在する自衛隊」と言われてきました。1990年に湾岸戦争があり、その後、日本も応分の人的貢献をせよという期待の中で、1992年に国際平和協力法ができ、それに基づいて、自衛隊のカンボジアでの国際平和協力活動が始まりました。その後の阪神淡路大震災の時には、自衛隊の出動が遅いというご批判を受け、それまで基本的には知事からの要請があってから出動だったのが、緊急時には自らの判断で出動できるようになりました。このようにして、自衛隊が実際に活動する機会が増えていきました。
2005年のイラク復興支援活動は、私にとってもインパクトのあるものでしたが、陸上自衛隊にとっても、初めて殉職者を出すかもしれないという危機感の中での活動でした。また、2011年の東日本大震災では、10万人の規模で活動をしました。
■カンボジアにおける地雷処理支援活動
最初に、退官後に携わっているカンボジアでの地雷処理支援活動についてご紹介します。私が参加しているのは、日本地雷処理を支援する会というNPO法人で、JMAS(Japan Mine Action Service)と言っています。これは自衛隊のOBたちが、自分たちの経験を国際協力に生かしたいと、2002年に立ち上げたものです。現在は、ラオス、カンボジア、パラオ、ミクロネシアで活動しています。パラオとミクロネシアは、先の大戦の時に沈んだ日本の船が、弾薬を積んだままとか、燃料が漏れそうなものがあって、それらの回収作業をしています。JMAS自体がその活動に直接関わるのではなくて、現地の人々に技術協力していくかたちでの活動をしています。
カンボジアの地雷・不発弾の汚染状況ですが、不発弾はベトナム国境からラオスにつながる所が多いです。これはベトナム戦争の時のものです。地雷はタイ国境に近い所が多く、こちらはカンボジアの内戦の時のものです。
地雷・不発弾による被害者は、2000年ぐらいまでは、年に2千名から4千名の死傷者が出ていました。その後、処理の成果が出てきてはいますが、昨年も44名の死傷者が出ています。
地雷には対人地雷と対戦車地雷があります。対人地雷は5、6㎏の圧力で爆発します。これは1個数百円ででき、埋めるのも簡単です。対戦車地雷は、大きさが30㎝ぐらいで、100㎏から200㎏の圧力が掛かからないと爆発しません。これの狙いは、戦車の履帯(キャタピラー)を切ることです。不発弾は、クラスター弾です。これは、アメリカがウクライナに供与したものと同じです。中にボール弾が500個ぐらい入った大きな爆弾を飛行機から落とし、中のたくさんの鉄球が破裂して人々を殺傷します。このうち約30%が不発弾となり、事実上の地雷となります。今、ラオスにもカンボジアにもまだ数千万発の不発弾が残っていると言われています。ちょうどボールぐらいの大きさで、子どもたちが手に取って遊んだりしますので、非常に危ないです。
地雷は人力か機械で処理をします。人力による処理は、防弾チョッキとフェースガードを着けてヘルメットをかぶります。ダイソンの掃除機みたいな金属探知機を持って、下にある円盤みたいな感知する所を地面から5㎝ぐらいのところで動かしていきます。感知したら、横から棒を突っ込んで少しずつ掘っていきます。縦から入れると圧力を掛けることになりますから危険です。そして針金みたいなもので刺していって、なかったらまた掘っていきます。その感触のために、手袋も外してやります。地雷ではない小さな金属片とかでも金属探知機が反応しますが、反応したものは全部調べなければなりません。気温が35度から40度ぐらいですから、集中力が4時間ぐらいしか持ちません。ですから、何もなくても1日20mぐらい、地雷が発見されると10mぐらいしか進みません。機械だと早く、コマツの地雷処理機は、ブルドーザーの前に爪が付いたローターが土を耕していきます。早いのですが、対戦車地雷と対人地雷が混ざった地域、それから民家が近い地域には使えません。やはり手作業に頼るしかありません。
もう一つ重要なのが、教育です。不発弾や地雷の写真を載せたノートを配布して、これらを見つけたら、遊んだり触ったりせず連絡するようにと、学校や村々で危険回避教育を行っています。その他に、地雷を処理した地域での農業支援活動や学校建設などの復興支援事業も実施しています。
先ほど言ったように地雷は埋めるのは簡単だし経費もかかりませんが、その処理には膨大な労力と時間が必要になります。ウクライナにも相当な地雷や不発弾があると聞いています。どうして将来に禍根を残すようなことをするのかと思います。ウクライナでもわれわれのノウハウが役に立つのであれば、積極的に支援していきたいと考えています。
■東日本大震災災害派遣活動
東日本大震災の派遣活動の際、自衛隊は、初めて、東北方面総監を指揮官として、統合任務部隊という陸海空を合わせた10万人規模の部隊の編制をしました。私はその中のJTF司令部の幕僚副長として従事しました。
震災については、3月の発生から8月31日に終結命令が出るまで、人命救助活動、行方不明者捜索、生活支援等を実施しました。原発については、放水作業や避難誘導支援を実施し、12月26日に終結命令が出ました。この間、私達の活動の合言葉は、「すべては被災者のために」でした。
行方不明者捜索については、海岸、海の中、湖、沼、用水路、土管の中、床下、あらゆる所でやりました。大川小学校の児童74名が津波で亡くなられましたが、ここでも、津波で堆積した土を全部はがして父兄が納得されるまで捜索活動をしました。学校から2㎞ぐらいのところに富士沼という周囲が4㎞ぐらいの沼があります。津波はここまで到達していましたので、この沼の水も全部抜いて捜索活動をやりました。
その他、給食支援、給水支援、入浴支援等、いろいろな被災者支援の活動を実施しました。
■東日本大震災で得た教訓
ここでの教訓の一つは、自己の許容限界を超えた情報こそ重要だということです。政府の中に、地震調査研究推進本部というのがあって、そこでは東日本大震災の前に、10年以内に高い確率でのマグニチュード7から8の宮城県沖地震と津波の予測をしていました。また、2001年に同時多発テロがあり、原発のテロ対策の必要があるという意見もありましたが、結局何ら対応はされませんでした。原発は安全である、原発は安全でなければならないという固定概念に囚われていたからです。その結果、防潮堤の強化もされず、今になって自己反省も含めて言いますが、災害対策の計画も訓練も、極めてずさんなものでした。
このような状況でしたから、実際に原発の事故が起きると、もともとの計画では自衛隊の任務になかった消防車やヘリからの放水活動まで急遽やることになりました。自衛隊の駐屯地に消防車はあるのですが、これは駐屯地の中の火災のためのもので、専門の消防隊員はいません。たまたま駐屯地消防隊の当番になっていた隊員が、一度も訓練したことのない原発に対する放水任務に従事せざるを得なかったのです。
政府の事故調査委員会の調査報告書には、「根拠なき安全神話を前提にして、あえて想定してこなかったから想定外であったにすぎず、その想定の範囲は極めて限定的なものであった。このような想定にとらわれた教育訓練をいくらやっても危機管理能力の向上につながるものではない」とあります。
今年の日大のアメフト部の麻薬に関する調査委員会の調査報告書がこれに極めて似ています。「立証されていない事実や立証される可能性が低いとみなした事実を、矮小化し、ときにはないものとし、不都合な情報には目をつぶり、与えられた情報を自分に都合よく解釈し、自己を正当化する姿勢がすべての場面で顕著である」と指摘をしています。東日本大震災は10年前です。アメフトの話は今年の話です。何も変わっていません。情報が得られても、自分が対応出来ない情報は無き者にしてしまう、このような落とし穴があるということを常に認識しておくことが重要だと思います。
もう一つは、情報そのままでは役に立たないということです。例えば宮城沖地震で想定された死者数何名、倒壊家屋数何棟と言ってもそれだけでは役に立ちません。実際には、亡くなられた方に対応するだけの火葬場がなくやむなく土葬しました。土葬の場まで運ぶのも自衛隊がやりましたが、震災後、霊柩車組合と葬儀組合から「どうしてうちに言ってくれなかったのか。我々が協力できたのに。」と言われました。つまり、死者何名がどのような意味をもつのか、情報を分析して評価をしていれば、組合の方々と事前に協力関係ができていたかもしれません。倒壊家屋についても、その中には東北の7カ所の製油所のうち4カ所の製油所も入っており、またタンクローリーも津波に流されたことで、病院も県庁も浄水場もテレビ局もみな非常電源の燃料がなくなり、パトカーの燃料までなくなるという危機に見舞われました。自衛隊の補給処で備蓄している燃料を緊急に配給して、何とか乗り切りました。倒壊家屋の中にどのような重要な施設があるか前もって分析して準備しておくべきでした。
もう一つの例は、2005年の台風14号の時です。私は宮崎の都城の連隊長でした。台風直撃の前日に災害派遣の準備をして、いったん隊員を帰しました。翌朝、知事から災害派遣要請があってすぐに被災現場の宮崎市に向け部隊を出動させましたが、都城のインターに着いた中隊長から、高速道路が通行止めだと言ってきました。その中隊は緊急対応のため通過を許可されましたが、2個中隊目からは、道路に大量の土砂が流れ込んできて物理的に通過できませんでした。結局、60名ぐらいの1個中隊だけで活動し、180名ぐらいの住民を救助しました。運良く犠牲者はおられませんでした。都城は盆地だとおぼろげながら思ってはいましたが、盆地だから、大量の雨が降ればこのような恐れがあることに、初めて実感として気づいたのでした。私の大失敗でした。
情報は重要ですが、そのままでは役に立たず、自分の任務に応じてきちんと分析・評価しなければ、このような落とし穴があるということです。
■イラク復興支援活動
イラク戦争終了後、2004年から2006年まで、自衛隊はイラクで復興支援活動に従事しました。派遣規模は約600名です。私は第8次隊として現地に赴きました。主に人道復興支援活動で、イラクの南部サマーワという所に基地を設営しました。比較的安定した地と言われていましたが、それでも、投石、デモ、狙撃、自動車爆弾や自爆テロなどの襲撃等に備えた構造の基地としなければなりませんでした。活動は、給水、医療、学校等の補修で、特に医療については、お医者さんの指導のほか妊婦さんへの母子手帳の普及活動も実施しました。それなりの活動ができたと思っています。
その活動を守るのが警備です。活動現場への移動はLAVという軽装甲機動車です。そして、活動現場では隊員は防弾チョッキを着用しています。この防弾チョッキは小銃弾を止めることができ、重さが12㎏ぐらいあります。そして銃を持ちます。この中には実弾が20発と、その他に100発の実弾を装着しています。警備隊員はすぐに引き金が引けるような態勢で警戒にあたります。手は絶対に銃から離してはいけません。そしてサングラスを着けます、これは隊員がどこを見ているのかが分からないようにするためのものです。
日々の活動を行うためのルーティンは、復興支援活動に出る前日夜に作戦会議をします。そこで、考えられる全ての脅威と対応について皆の認識を統一します。そして当日早朝、私は多国籍軍から来るインフォメーションサマリーを読んで全体の状況を把握します。幕僚は幕僚で、サマーワの朝の状況の確認をします。そしてこれらの情報を総合して、隊員を出すかどうか、日々決心をします。活動を実施するとなれば、警備中隊は基地の中でリハーサルをし、それから出発するという手順を踏んでいました。
■イラク復興支援で得た教訓
イラク派遣の準備訓練は、6カ月前からやり始めたのですが、初めは、車両を川の中に落としたり、人をひいたり、空砲ですが暴発はさせたりという状況でした。原因は、隊員達がイラクの厳しい状況を日々耳にして浮き足立ち、自分たちが培ってきた基礎動作を全部忘れて対応しようとしていたからです。
これを改善するために、まず基礎の基礎である「気をつけ」とあいさつから徹底することを指導しました。朝、集合して「気をつけ」が掛かると、「目を動かすな」というところから始めました。それから、隊員同士がすれ違うときは敬礼をして必ずアイコンタクトをすることを徹底しました。何か不安などがあると人は目をそらします。気になる者がいれば、個別に心情を確認するようにしました。また、車に乗るときも、まず車の前に乗員が整列して各人の任務を呼称し、「乗車用意」「乗車」の号令で乗車するという入隊当初に教育された基礎動作を改めて実施させました。すると不思議なのですが、全体として部隊がだんだん落ち着いてくるが分かるのです。そして事故も起きなくなりました。その時に基礎が極めて重要だということをあらためて感じました。
もう一つは、「訓練は実戦の如く」ということです。私達は、あらゆる脅威を想定して準備しました。現地は市街地なので、2、30mの距離で射撃をしなければなりませんから、至近距離射撃というのを徹底して、特に警備中隊では数多くの実弾射撃訓練を実施するよう命じました。デモ対処訓練もやりました。警察は得意だと思うのですが、自衛隊はこの訓練をやったことがありません。そこで、他の部隊にデモ隊になってもらって何度も訓練しました。デモ隊側の隊員もターバンを巻いたりして本気でやってくれました。当初、決められた手順通りにやりますがなかなか上手くいきません。「止まれ」と言ったのにデモ隊は止まらない、威嚇のために銃口を向けても止まらずだんだん接近してくる。威嚇射撃をするとデモ隊は更にヒートアップする。どうすれば良いか試行錯誤を繰り返しながら何度も訓練を行いました。
この訓練が、実際に役に立ちました。ルメイサという所で、養護学校の竣工式を行っているとき、民兵組織5、60名に襲撃を受けました。警備隊員は、暴徒と接触した時に蹴られたりしましたが、車両の中に待避して状況を見守りました。サイドミラーはほとんど壊され、バンパーとかも曲げられましたが、われわれが銃を使うことはありませんでした。暴徒が銃を持っていなかったからです。暴徒が銃を持っているかどうかなど状況をつぶさに確認しつつ冷静に対応出来たのも訓練のお陰です。この時、浮き足だって銃を撃っていたら、その後の派遣活動に大きな影響を与えていただろうと思います。本当に、「訓練は実戦の如く」ということが重要だと感じた次第です。
■指揮官の心得と責務
私が自衛隊時代に感じたことは2点です。一つは、「人事を尽くさなければ天命は待てない」ということです。「人事を尽くして天命を待て」という言葉はありますが、私のような凡人は、すべてのことをやり切らないと天命を受け入れられるだけの覚悟はできないという意味です。イラクでの私の指揮官としての任務は、復興支援活動はもちろんなのですが、隊員を全員無事に帰国させることでした。準備すべき訓練はすべてやりましたが、それでも、隊員を死なすかもしれないという懸念は心のどこかにあり、どうも落ち着かない。その理由は、指揮官としての任務を達成出来なかった時にどのように身を処すか、指揮官としての心の準備が万全ではなかったからです。
派遣直前に、私は妻を呼び真剣な顔で聞きました。真剣な顔をしたのはプロポーズ以来でした。「あなたも自衛官の妻として、私が死ぬことについての覚悟はあるだろうけれども、今回は、隊員が死んだときのことで、そのときに、自分は責任を取って自衛隊を辞めたい。」と話しました。妻は即座に、「いいよ。私が働くから」と言ってくれました。その言葉に任務達成できなかった時の身の処し方も明確になり、そして指揮官としての覚悟がやっとできたように思います。
もう一つは、「原点に立つ」ということです。隊員は、困難な状況にあるときや困ったときは指揮官の顔、それも目を見てこちらの心の中を見てきます。そして、そのような時ほど状況判断に迷いますが、迷った時ほど原点に返る。私の場合は自衛官ですから自衛官としての本分、つまり国民の生命と財産を守ることに立ち返ることが重要ということです。
震災の後、私達幕僚は、自衛隊の活動の教訓事項をまとめました。その内容は多少の問題はあったものの、全体的には上手く活動出来たというものでした。そこで指揮官にこの内容を報告しましたが指揮官の指導は、たった一言「もっと助けられなかったかな」と言われたのです。その指揮官の目は、助けられなかった被災者のほうを向いていたのです。私達幕僚は、自衛隊の活動を多くの人に感謝され、そのことにいい気になっていたようにも思います。指揮官の一言で、私は自衛官という原点を改めて認識し、自分はまだ浅いなと反省した次第です。
■質疑応答
〇高橋 昭和41年卒の高橋です。2011年東日本大震災の時の総理大臣は、私の友人でした。大学で一緒にヘルメットをかぶっていた仲です。
1995年の阪神淡路大震災の時に、災害対応現場での指揮命令系統はどうだったのでしょうか。アメリカでは、陸軍でも海兵隊でも関係なく、現場に先に着いた者がそこの指揮を執るという暗黙のルールができているようです。日本ではどうなのでしょうか。それから、違う組織間の情報ネットワークはできているのでしょうか。
〇立花 われわれは、法律に基づいて行動しています。災害基本法には第一次的な責任は地方自治体にあるとなっていますので、地方自治体の中に指揮所をつくって調整をします。1995年の阪神淡路大震災の時には、まだそのような調整はできていなかったというのが正直なところです。その後、いろいろな災害を経験して、自衛隊、警察、消防、地方自治体、それぞれが共同して対処できるような態勢になってきています。ただ、現場レベルでの横断的なネットワークは、まだこれからです。
〇中塩 平成元年卒の中塩です。東日本大震災の災害があったりして、今でこそ、国民の自衛隊という感じになっていると思いますが、例えば、過激派が陸上自衛隊員を刺殺したという話があったり、自衛隊の子弟の小学校入学のボイコット運動があったという話も聞きます。そのような、国民の自衛隊になる前の時代にでも職務を全うされたことの原動力は何だったのでしょうか。
〇立花 あるインタビューで、「自衛隊反対の人がいますが、どう思われますか」と聞かれたときに、自衛官の答えとして、「その人たちも助けるのが自衛隊なのです」というのがありました。そこにわれわれの自衛官として培ってきた精神があるのだろうと思います。
〇林 昭和58年卒の林です。埼玉県の戸田市で市議会議員をしています。今、首都直下地震の対応に力を入れているところです。自衛隊の方から救援を受けるという前提で、自治体がそのときまでに特に力を入れて備えるべきことは何でしょうか。
〇立花 一番重要なのは、住民の皆さんの意識だと思います。自助、共助、公助ということがよく言われます。自衛隊はすぐには行けません。まず初めは、自分のことは自分で守り、それから、近所同士でお互い助け合うということです。われわれ自衛隊が、食料や水とかの被災者支援活動をし始めるのは、72時間以降だと考えていただきたいと思います。72時間以内はとにかく人命救助を優先します。それまでは自助で、それから共助でやっていただくということが重要なことだと思います。
〇徳島 平成10年卒の徳島です。私もラグビー部出身です。想像を絶するような緊張感の中で、いろいろな判断をされてこられたと思いますが、指揮官としてのリーダーシップにおいて大切なことは何でしょうか。
〇立花 まずは自分自身の覚悟だと思います。イラクで、襲撃を受けたら、その襲撃を受けた隊員をすぐに助けに行くか、それとも、二次攻撃を避けていったん引くかを、隊員同士で相当議論したけれども結論に至らず、会議の席で指揮官としての決心を求めてきました。「それは助けに行くんだ。二次被害はあきらめろ。俺が指揮官だから」と応えました。どちらか1つを選ばなければならない時にあやふやにせず明確に指示を出す。明確な指示を出すには、自分なりの指揮官としての覚悟が大切だということです。
それから、一番駄目な指揮官というのは、やる気があって無能な奴だとよく言われます。無能な奴でやる気がないのは、スタッフがやってくれます。やる気があって無能な奴は、でたらめな命令ばかりで、隊員を危険な目に遭わすことになります。知見を積んで自分を磨いていくことがまず第一歩だと思います。
■会長あいさつ
〇伊藤 昭和42年卒の伊藤です。今日はありがとうございました。
カンボジアのアンピルで文民警察官が亡くなった時、私も現地に行きました。そこは本当に電気も水もなく、道もでこぼこでした。その時、まだたくさん地雷があると厳しく注意されました。ですから、立花さんは、本当に厳しい状況の中で大事なお仕事をされていると思いました。
また東日本大震災の時には、私は内閣にいて全体的な指揮をやっていました。自衛隊10万人というのは、私が独断で決めました。それにはもちろん根拠はあったのですが、それぞれの市町村が崩壊していた中で、自衛隊が本当に大きな仕事をやっていただいたと思っています。
また、原発にも、自衛隊、警察、消防に消防車を出してもらって放水をお願いしたのですが、爆発事故があったり、大きながれきが降ってきたり、本当に危ない中で最後まで頑張っていただきました。
今は、NPOの活動を続けておられるそうで、これからも国のために尽くしていただけると心強く感じた次第です。一つの判断が部下の命に関わることもあるという厳しい状況の中で、現場の指揮官を経験してこられた、自衛隊の中でも数少ない人材でいらっしゃるのだと思います。
これからもますますご活躍されることを期待しています。
(終了)