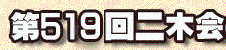
|
<女性>作家であること〜樋口一葉をめぐって
お茶の水女子大学大学院助教授 菅聡子氏(昭和56年卒)
2005年3月10日(木)学士会館 1 はじめに 今日は、樋口一葉という女性作家の登場の仕方、あり方を通じて、現代にも通じる問題を提起していきたい。 2 出版メディアにとっての「女性作家」の意味 昨年の芥川賞における盛り上がりぶりを見て、「女性作家にとってビジュアルは必要か、容姿は影響するのか」ということを改めて思い知らされた。 
女性にまつわる事件へのメディアの取り上げ方には、「美女」「高学歴」「エリート」などの言葉、あるいはその否定形がついてまわる。芥川賞も最近このようにメディアで長時間扱われたことはなく、二人の若い女性作家がメディアに流通する、ということは出版界に多大な経済効果をもたらしたのである。 このような女性作家におけるビジュアルとメディアと経済効果という三つの要素の関係性は、女性作家が文壇に本格的に登場した時から始まっていた。当時商品価値の最も高い女性作家であったのが、樋口一葉である。 一葉の場合、「独身の娘にもかかわらず遊郭の話を書く」「男性新人作家のものより優れている」ということで、彼女の商品価値は明治29年の死の直前に最高潮に達していた。 明治20年代は近代的国民国家の根幹が作り上げられた時期であり、近代的な出版・流通機構、そして文壇というものも成立した、非常に興味深い時代である。 また、文学における近代、とうのは出版メディアが成立した時代でもある。明治20年にできた当時の一大出版メディアである博文館は、図書・雑誌の取次の東京堂、紙の博進堂用紙店、さらには印刷所をも持つものであった。 博文館がいち早く目をつけた、当時最高の商品価値を持った女性作家が一葉である。 
明治28年の「文芸倶楽部」臨時増刊の「閨秀小説号」はそれまでの女性作家への関心を一気に顕在化させるものであった。その巻頭で、当時の読者たちははじめて女性作家たちの「肖像写真」を見ることになる。普通の家の女性が不特定多数の人々の前に顔をさらすなんてとんでもない、とするのが当時の女性をめぐる道徳であった。 現代の女性作家は自分自身を戦略的にプロデュースしている。文庫本にはプロの撮影したソフトフォーカスの写真を載せていたりする。男性作家にも、身長まで公開している例すらある。 ではどのような文脈で明治のメディアは女性作家の肖像写真を載せたのか?花鳥風月の中で女性作家を花に見立てているような構図は、同時期に発売された同誌のレギュラー号表紙を飾る芸者の構図とまさに同じである。その背景には、両者の「顔」への読者の視線、さらにいうなら欲望の視線が共通していることがあげられる。 肖像写真は読者の間を流通し、作家自身が作品の前に流通するという事態を引き起こした。それは近代的システムにおいては避けられない状態であった。一葉のもとには彼女の商品価値に目をつけた出版ビジネスが次々に訪れることになったのである。 一葉はそれを「あやしきこと」といっている。一葉は、自分に向けられた関心の根源が女であることにある、ということを的確に掴んでいた。彼女は自分を当時流行した娘義太夫に例えている。 一葉が残した45冊の日記はさまざまな形のものであるが、この日記によって、彼女は立体的にとらえることができる。後になってまとめて書いた一連の出来事を編集したもの、脚色化されたもの、実況中継のような事件の描写、などが和紙に草書体で墨書されている。 それは活字となった現在のものとはまったく違う、身体性をも感じるものである。 一葉は「薄幸の閨秀作家」というイメージが強いが、生きているときにすでに評価を得ていることを考えると、作家として決して不幸であったわけではない。日記の文章には彼女自身得意になっているところも見えるが、だんだん「不機嫌」になって虚無的になっていく。私の一葉への関心も、そこから始まった。 一葉は当時としては非常に珍しい「女性戸主」であった。「女だけれども」「女でありながら」戸主である、という屈折した立場であった。職業もなく、父親の残したものは借金だけであったのに、17歳の一葉は母と妹の生活を背負う立場となる。彼女は、一人の作家として認められれば、一人の「個」として認められる、と思い描いたのではないか。 しかし作家として世に知られ注目されればされるほど、そこで取り上げられるのは女性としての性であった。これは百年経った現在も似たような状況である。 一葉は最初に評価された時から、ただの作家ではなく「女性作家」なのだ、という世間の視線に直面した。これは、女性が社会に進出した際の取り上げ方が往々にして過剰であり、何かあればバッシングを受ける、という現在の女性への視線にも共通するものである。 私自身、今回の一葉の新札への登場も、その「肖像」の採用を素直に喜べないものがある。 3 一葉の視点 一葉の作品はどこに目を向けていたのか? 一葉の作品で知られているのは明治27年の「大つごもり」後である。「大つごもり」以前と以後ではその作品世界はかなり変わっている。 「大つごもり」以後、彼女はそれまで描かれえなかったさまざまな境遇の女性の姿や苦悩と同時に、社会の弱者の姿を描き出すようになった。「大つごもり」には下女奉公に耐える女性が盗みへと追い詰められるプロセスが描かれ、「十三夜」では女性と家との関係への描写が見られる。そこには、母親、娘として生きる女性が「私」というものを求めたときの姿が描かれている。また、「にごりえ」「たけくらべ」には、身を売る女性たちにとっての「生きることとは何か」が描き出されている。そして「わかれ道」では、当時としては珍しい自活する女性が最終的に妾になる、ということの意味を、弱者である少年の目から描写している。 なぜ「大つごもり」が転機なのか。それは彼女の2回の転居が大きく影響している。明治26年、一葉は下谷龍泉寺町で子供相手の店を開き、社会の下層の人々と交わることとなった。さらに彼女は本郷丸山福山町に転居するが、そこでも彼女は酌婦の代筆屋など、同時代の女性作家には全く不可能であった体験をしている。彼女自身が自分の属していた階層から「越境」しているのである。 当時の女性たちも、家、すなわち家父長制度の内部にいる女性たちと外部にいる女性たちの二つに分断されていたわけだが、彼女自身がその二つの階層を越境する作家であったのである。そのことが作家としての彼女のまなざしを非常に深めていったと考えられる。 4 むすびにかえて 「珠玉の短編」、といった一葉の作品につきまとう叙情的なイメージとは裏腹に、彼女の作品は非常に冷徹なものを抱え込んでいる。明治社会の明るい部分から排除された人々の生き方を冷徹にとらえているのである。 これを機会に一葉の作品を触れてみようか、という方には、その部分を是非お考えおきいただければ、と考えている。 |
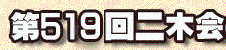
|
|||||||||||
|
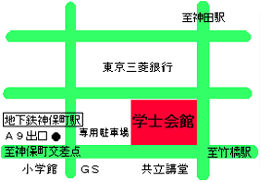 学士会館
学士会館